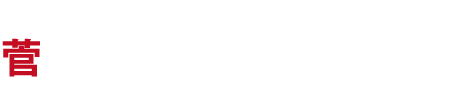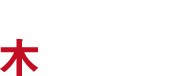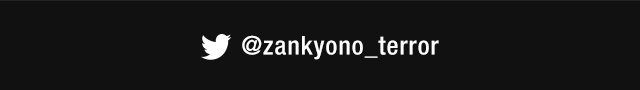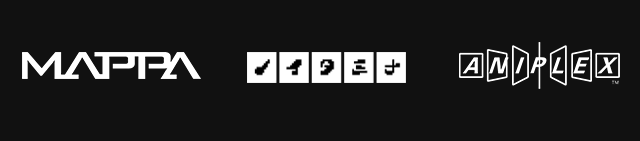- ――『残響のテロル』の企画の経緯を教えてください。
- 渡辺 2007年ぐらいから2012年の『坂道のアポロン』まで、全然仕事をしてなくて休んでたと思ってる人もいるらしいんだけど、実はその間に何本もオリジナルの企画を考えて準備していたんです。でも、不景気とかでなかなか企画が通らなくて、どれも実現しなかった。『残響のテロル』はそのころに考えたオリジナル企画の一本です。企画自体は震災より前だったから、もう4、5年前になるのかな。
- ―― 以来、実現の機会を狙っていた、と。
- 渡辺 そうですね。それで、3年位前にフジテレビさんから、原作ものである『坂道のアポロン』のオファーが来た時に、「こんなのもあるけどやりませんか」と『残響のテロル』の話もしたんです。そしたらノイタミナの山本幸治プロデューサーから「では『坂道のアポロン』1本だけではなく、その後のオリジナル企画についても併せて考えましょう」との話になり、ようやく実現することになったんです。
- ―― 企画を思いついた発端というのは?
- 渡辺 近年、世界のあちこちでテロ事件が起きているけど、どこかそれは遠い国での出来事、という感じが日本人にはあると思う。でも、東京のど真ん中でいきなり連続爆破テロが起きたらどうなるだろうか?自分たちはどう対処するだろうか?犯人が、十代の少年だったら?現代テクノロジーを使いこなして、スマホ一台で日本を手玉に取るような、そんな奴らが現れたら?そんな所から発想していきました。そして、今の日本で実現可能なテロ行為を考えていくと、自然に今の日本という国のシステムと、その成り立ってきた過程を考えざるを得ない、という事になっていきました。
- ―― 今はまだ多くが明らかになっていない『残響のテロル』ですが、どのような内容になるのでしょうか。
- 渡辺 ひとつはアクションサスペンスとしての側面があり、そういう見方で言うと自分がつくってきた作品の中でも、意外と現代アメリカのアクション映画に近いかも知れない。もうひとつの側面として、青春ものというか、十代のころの若さ、未熟で不安定で、でもエッジが尖っていて挑戦的な感じ、そういうものを描いてみたいという気持ちがありました。その両者が混ざりあってるんじゃないかな。ジャンルで言うと、青春アクションサスペンス、そんなジャンル聞いた事ないけど(笑)まあ常に新ジャンルを開拓しようと。あとは最近、向こうの映画監督がテレビシリーズを手がけたりして海外ドラマのクオリティがすごく上がってて、そういう海外ドラマもちょっと意識してますね。単純に映画より尺が長い分、ストーリーやドラマ的な要素をたくさん詰め込めるし。
- ―― 海外ドラマですか。
- 渡辺 ええ。最近のアニメと同じようなものを自分が作っても仕方ないし、もっと広い層に見てもらえる作品を目指してます。ただ、どうもテロを扱った作品とかいうととっつきにくいイメージを持たれるようなんで、親しみを持ってもらえるように、最近は「『24』みたいなドラマです」と言い張ってます(笑)。あとは毎回、テロリスト“スピンクス”とそれにまつわる謎解きを毎回盛り込んでいるので、「『SHERLOCK』みたいな要素もあるぞ」ということで(笑)。
- ―― 現在発表されている「ふたりの少年が、“スピンクス”を名乗り、日本中を巻き込んだゲームを始める」という設定を見るに、渡辺監督のフィルモグラフィーの中でも一番挑発的な内容になるのでは、と想像するのですが。
- 渡辺 そういうのは意識してやってる訳じゃなくて、自然な流れですね。特にオリジナルのアニメ作品というのは、まったくのゼロから世界観を作っていくわけで、何の根拠もないところからは作りにくい。だから、自然に自分というものが出てしまうんです。たとえばの話、同じ世界に生きていてもその世界をどう捉えるかは、その人によって違う、欺瞞に満ちた絶望的に生きにくい世界だと感じる人もいれば、とくに不満もなくて平和でいい世界だと感じる人もいる。その時に自分が世界をどう捉えているか、どう感じているかがオリジナルのアニメだと自然に出てしまうんです。
- ―― キャラクターデザインは中澤一登さん、音楽は菅野よう子さん。渡辺監督とは縁の深い二人が今回も参加しています。
- 渡辺 二人の共通点は、あまり説明がいらないとこですかね。作品を作るときって、「こういうものがやりたい」というのを、スタッフにそんなに上手く言葉で説明できるわけじゃない。むしろそういう言語化される以前の感覚、みたいなものが大事なんで、なかなか人に伝わらない事が多いんです。たとえば、「〇〇みたいな作品」みたいな説明を求めてくるスタッフもいるんだけど、他の何かに似てる作品なんか作りたくないんで(笑)。そんな中、この二人はくどくど説明しなくてもいろんな事を分かってもらえる。あと、もうひとつこの二人の共通点は、同じテーマをやるにしても、一人でも多くの人に伝わるような形でプレゼンしようとする、ポピュラリティみたいなものを常に意識して仕事をしてることで、それはとても有り難い。
- ―― 最後に『残響のテロル』にかける意気込みをお願いします。
- 渡辺 これは長年やりたかった企画がようやく実現した、入魂の一本ですし、この作品を世に問いたい、という気持ちで作ってるんで、是非、見て欲しいですね。
- ―― ありがとうございました。

- ――『残響のテロル』の企画の第一印象を教えてください。
- 中澤最初にビジュアルイメージと簡単な内容を書いた企画書を見せてもらいました。でも、その時点ではまだ全貌が決っていたわけではなくて。だから、また渡辺(信一郎)監督と仕事をするのがおもしろそうだ、というのが第一印象でした。
- ――渡辺監督との仕事は楽しいですか?
- 中澤そうですね……。作業中はとてもツライですが終わった後は、楽しかったことしか覚えていない、という感じですね。僕にとって渡辺監督は、全面的に信用できる演出家の1人なんです。ちょっと時間はかかっても任せておけば間違いのないものが出来上がってくる。その分、僕は絵描きに徹することができるのが、とてもやりやすいところです。
- ――中澤さんが渡辺監督の存在を意識したのはいつごろだったのでしょうか。
- 中澤『マクロスプラス』(1994年)です。渡辺監督さんに言わせると、あの作品は総監督の河森正治さんの世界だということなんですが、僕には、すごくおもしろかった。キャラクターや世界観が、マンガっぽくなりすぎず、アートっぽくなりすぎず、心地よく見られるちょうどいいバランスで成立していて、そこがすごいな、と思って。それってどこか一つの目標を目指す姿勢では到達できないことなので、すごいことだと思いました。
- ――渡辺監督は、中澤さんとのお仕事は説明しなくても伝わるのでやりやすい、とおっしゃっていました。
- 中澤ああ、それは僕もそう感じます。「低温で青白い炎が静かに燃えている」感じのキャラクターやストーリー、画面を好む趣向が、似てると思います。けど渡辺監督のほうがずっといろいろ考えてらっしゃいますが。渡辺監督は心の奥底に澱のようなものをため込んで、そこまで深く潜って考えたものをドンと出してくる感じです。表層をさーっと行こうとする僕とはそこが違う(笑)。ただ渡辺監督と作品をやる時は、僕なりに「結論」はなんとなく見えているつもりなんです。そこにいく過程については考えも違ったりするんですが、「最終的にこういう作品にしたい」というところは大きなブレなく理解しているつもりです。だからスケジュールが許す限りは、そこに準じていこう、と。目指すところに間違いはないはずと思って作業をしています。
- ――ナイン、ツエルブ、リサというキャラクターはどのように生まれたのでしょうか。
- 中澤具体的なことは結構前なんで忘れちゃってはいるんですが最初にイメージしたのはドラクロワの「民衆を導く自由の女神」とTOTOの「子供の凱歌」です。僕がデザインする時、最初はまず直感なんです。渡辺監督が自分の中のイメージをいろいろ語るのを聞いて、直感で自分の頭に浮かんだ画像を元にラフを描くんです。その時は監督の中にもまだ確固たるものがあるわけではないので、こちらで何パターンか用意して、渡辺監督に選んでもらうんです。そこで選ぶ時に、渡辺監督が絶対正しい選択をするのはわかっているんで。ただ、その後で各キャラクターにまつわる情報を具体的にのせて、デザインを固め始めると、渡辺監督のイメージからまた離れ始めてしまったりするんですが。
- ――離れちゃったりするんですか。
- 中澤離れますね。マンガとか1枚の絵であれば最初のラフに近い方向性でいけるのかもしれません。でも、アニメはキャラクターを立体として取り扱うので、どんな角度から見ても成り立つようにしなくてはならない。その過程でズレが生じるんです。
- ――今回は渡辺監督から方向性について注文などあったのでしょうか。
- 中澤方向性について具体的なことを言われたわけではないですが、初期のキャラクターイメージ画を見た時、若干モード系な方向性を目指しているんだろうなという感触があったので、そこは崩さないように意識しました。でも、絵コンテ見たら「あれ?違うな」と思い修正して。絵コンテ見ると、すぐにキャラクターのイメージわくので、むしろどんどん絵コンテを描いてくれると助かるんですけれど。
- ――ヒントとして実在の役者さんの名前が出たりするんでしょうか。
- 中澤決してそのまま似顔絵を描くわけではないですが、ヒントとしてわかりやすいので出ますね。でも、それが渡辺監督と僕で想定する役者さんのキャラクターがかなりずれていたりするんで、そこはかなり難航します(笑)。
- ――今回はどんな名前が挙がったのでしょうか。
- 中澤リサについて渡辺監督は連続テレビ小説の某女優さんの名前を挙げたんですが、僕はまったく違う人を想定していて。だからキャラを描いてもなかなかOKにならなかった(笑)。ナインとツエルブも同じ感じでした。こういうのは意見がまとまるとかそういうことではないので、リテイクを重ねつつ、あとは締め切り時間次第ですね。あと設定ってあくまで制作の前段階の作業なんです。
- ――前段階ですか。
- 中澤はい。機械もそうですが、緻密に設計して組み立て完成したとしても、使ってみて不具合を確認して、もう1回バラしてパーツを磨いて組み立て直さないとうまくいかないですよね。キャラクターも設定しただけで完璧ではなく、本編の中で描きながら熟成させる時間と調整が必要なんで、何話か作業をしてみないと固まりきらないんです。
――今回のストーリーについてはどんな印象を持たれましたか?
中澤ストーリーに関しては、一ファンの視線で「はー、これはまた過激な内容だな」と。現状、どんな結末を迎えるのか僕は知らないので、楽しみにはしていますが、いつにも増して内角ギリギリですよね(笑)。僕がピッチャーで「このコース投げろ」といわれたら即座に首を横に振るところですが(笑)、渡辺さんのオリジナルなんで、そこは渡辺さんを信じています。そして僕にも着地点はうっすらと想像できるので、そこにいくにはどう効率よくやれば、たどり着けるか、そういうことを考えて自分が手伝える精一杯のサポートをしていきたいと思ってます。
――ファンの方にメッセージをお願いします。
中澤番組を見ていただいて、楽しんでいただければうれしいです。

- ――『残響のテロル』に参加した経緯を教えてください。
- 立川 プロデューサーの大塚(学)さんから連絡をもらいました。もともと渡辺(信一郎)監督の作品には興味があったので、お会いしていろいろ説明をうかがい、そこで「では、お願いします」となりました。実はそこには渡辺監督も同席していて、作品の“核”の部分を説明してくださったんです。逆に僕がこれまでやってきた作品について聞かれたりもしました。
- ――その時が渡辺監督と初対面ですか。
- 立川 そうです。渡辺監督は雑誌などにのるときはいつもサングラス姿で、作品も切れ味あるイメージのものが多いので、ちょっと怖そうなイメージ(笑)を勝手に持っていたんです。でも、実際に会ってみると、すごく物腰の柔らかい方でした。お話をしてみると、当然なんですが、監督っぽい人だなと。スタッフとスタッフの間をとりもったりするところなどにいろいろ気配りされる方でした。
- ――『残響のテロル』という作品の第一印象を教えてください。
- 立川 ある程度リアルな世界観でテロリストを取り扱うという作品というのは、TVではなかなかなかったなと。僕はリアルなテイストの作品は好きなので、おもしろそうだなと思いました。もちろん描かれる内容には過激な部分もありますが、物語をちゃんと先まで見てもらうと、テロの理由にもちゃんと骨太なものがあるんです。だから演出サイドの人間としては、やりがいのある題材だなとも思いました。
- ――今回は助監督としての参加ですね。助監督というのはどういうポジションの役職なのでしょうか。
- 立川 監督というのは忙しくて、下手をすると週の半分はスタジオ外で編集や音響の作業をしているのです。助監督はその監督と現場を繋ぐのフォロー役になります。背景打ち合わせ、グラフィック打ち合わせ、3DCG打ち合わせ……。そういう各パートとの打ち合わせや成果物のチェックについては、事前に監督と僕が要点だけ話し合っておいて、僕のほうで進めることになっています。監督の時間のない時にはコンテの修正もします。あとはポイントとなる回のコンテ演出ですね。たとえば前半では第1話は演出、第2話で絵コンテ、第5話で絵コンテ・演出を担当しています。
- ――作品を演出する上で気をつけている部分はどこでしょうか。
- 立川 いわゆるアニメっぽい画面作りではなく、映画らしい構図とか画面作りを意識しています。たとえば画面手前には光を当てて、逆に画面奥は影を強くするなど重厚な雰囲気のある画面を作るとか、そういうことを意識しています。僕自身、そういう映画を意識した画面作りをすることが多いので、渡辺監督がこの作品でやろうとしていることはよくわかっているつもりです。ストーリーが練られている作品なので、映像的にも繰り返しの鑑賞に耐えられる作品にしたいと思っています。
- ――ストーリーの前半では、“スピンクス”がクイズで次の標的を告知するなど、謎解きの要素も多いそうですね。
- 立川 謎解きで難しいのは、ちゃんとそれが視聴者に伝わるようにしなくてはならないことです。映像って流れていくものなので、ポイントポイントでしっかり、謎解き時をわかってもらえるようにしないと、視聴者が置いてけぼりになってしまうので。そこはわかりやすくするように注意をしています。
- ――ナイン、ツエルブ、リサという3人のキャラクターについては、どのようにとらえていますか?
- 立川 ナインとツエルブがどうしてテロを起こしているのか。それはストーリーの展開とともに明らかになっていきます。物語がある程度進むと、序盤でどうしてこのキャラクターがあんな表情をしていたのかわかって、いろいろ印象が違っていくと思います。行為そのものは理解出来なくても、その時のナインとツエルブの心情には感情移入できるようになってますね。リサは、最初は傍観者としてナインとツエルブのやることに巻き込まれるんですが、それを通じて、リサが変化していきます。そんなリサの変化が、ナインとツエルブにも影響していって……という流れになるので、実はリサがこの作品の起爆剤といってもいいかもしれません。僕が本読み(脚本打ち合わせ)に参加した時は、そういう各キャラクターの心情を中心に、意見を言うようにしています。
- ――『残響のテロル』は立川さんの監督作『デスビリヤード』とも共通する部分はあるのでしょうか?
- 立川 ありますね。『デスビリヤード』と『残響のテロル』では、、ヒリヒリした緊張感と描こうとしているものが共通していると思いました。『デスビリヤード』は「生きているとはなんぞや」ということを、臓器をかけたビリヤードの勝負という設定を通じて描きました。『残響のテロル』は、もうちょっとリアルな設定で似たようなようなことを描こうとしている感触があります。そういう意味では、絵コンテを描くにしても、無理に「渡辺監督風にしよう」とか思うことなく、とても素直に作業ができています。
- ――ファンの方にメッセージをお願いします
- 立川 最近のTVアニメにはないリアリティある雰囲気と、と骨太なテーマの作品です。お楽しみにしていてください。
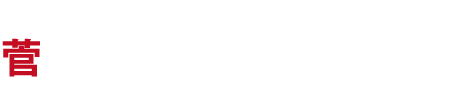
- ――『残響のテロル』への参加の経緯を教えてください。
- 菅野 この作品の直前私は、NHK朝ドラの作曲をやっていたのですが、そちらではあまり扱われない暴力性など悪いコ成分が自分の中で溜まって来ていたところにオファーがあり、こういうの待ってましたという気持ちでお引き受けしました。
- ――作品内容の説明を受けた時の第一印象は?
- 菅野 蝶。飛ぶ。壊れやすい、はかない。音がしない。
- ――今回の音楽について渡辺監督からはどんなオーダー、キーワードが出ましたか。
- 菅野 主人公達が子供のころから聞いている音楽のサンプルとして、アイスランドの音楽を聞かせてもらいました。キーワードは明かしてしまうとネタバレになるのでそれ以上は内緒。
- ――菅野さん自身は『残響のテロル』の音楽にはどのようなものがふさわしいとイメージしましたか。
- 菅野 北の音楽を聞いて育ったという手がかりと、主人公達が育った場所に近い雰囲気の場所に行って想像し、彼らの体感温度を表すような音がふさわしいと思いました。
緊張感があり、研がれていて、冷たい響き。
- ――渡辺監督との仕事が魅力的/刺激的な理由を教えてください。
- 菅野 圧倒的なセンスは言うまでもないですが、音楽が大好きで、音楽をすごく大切にしてくれる。どんな曲でも宝物をもらったように受け取ってくれて、大事にしてもらっているなあと感じます。
- ――菅野さんから見た渡辺監督はどんな方ですか。
- 菅野 飄々とした人。懐の深い人。美意識のある人。
- ――菅野さんから見た『残響のテロル』という作品の魅力を教えてください。
- 菅野 この世界をぶっ壊したいというのは、なかなか口にしづらいけれど、多くの人が感じていることでもあると思います。

- ――第1話はとてもインパクトある内容でしたね。
- 石川 そうですね。絵がリアルで、ぞわぞわ鳥肌が立つような感覚がありました。第1話に限らず今後も普段見たことがあるような風景がバンバン出てきて、映像を見ていると、現場が本当にあるニュースのような距離感でモニターを見入ってしまいます。そこにさらに深いドラマが載ってくるので、本当に目が離せない作品だな、と。今という時代にこういう題材を使うというのは、非常に勇気のあることだと思いますが、考えさせられることがたくさんあって、放送を見た方の心の中にいろいろな考えや、思いが浮かび上がる作品になっています。僕自身、決して絵空事ではなく、現実に起きている出来事のように感じており、視聴者のみなさんの心にも深く刻み込まれたのではないでしょうか。
- ――ナイン役を演じるにあたって、渡辺(信一郎)監督からはどんな説明がありましたか?
- 石川 オーディション用のセリフをいただいたナインの第一印象は「ひどく冷たい人間だな」というものでした。でもオーディションで演じる前に渡辺監督から説明がありました。そこで渡辺監督から「ただただ冷たいわけではなく、いろいろなことを考えた上でのセリフだということをわかってやってほしい」という趣旨のことを言われ、そこを念頭に置いて演じました。
- ――実際にアフレコが始まってからは、どうでしょうか。
- 石川 オーディションと違うのは、共演者がいるということですね。たとえば斉藤(壮馬)さん演じるツエルブは非常に変わっている、浮いた存在ですよね。そうすると一緒にいるナインも若干ずれていたほうがいいというか、周囲に馴染みすぎないほうがいい、ということは意識して演じています。
- ――ナインは、第1話を見るとツエルブよりも常識人にも見えますが。
- 石川 ナインは常識人であろうとはしているんです。なぜかというと、事を運ぶためにはそのほうが有利だから。合理的に物事を進めるにはどうしたらいいかを常に考えているから、そう見えるんだと思います。それに比べてツエルブは、横道にそれがちで、その点でも対照的な二人ですね。ナインはそんなツエルブのことをちゃんと理解して、いろいろ察しているんですが、僕自身からするとツエルブはわからないところが多いし、時々、いらっとすることもありますね(笑)。
- ――そんなナインとツエルブに関わることになるのが三島リサです。
- 石川 リサは序盤は、精神的に束縛されている状況が多くて、セリフも少なく、なかなか人柄が見えてこないんですよ。そんな中で、種崎(敦美)さんは、息づかいを一つ一つ気を遣って演じていて素晴らしかったですね。僕ら、渡辺監督から「自然に演じてほしい」「演技をしていると感じさせないでほしい」と言われているのですが、種崎さんの息は、安易に音にする息ではなくて、憧れましたね。本当にマイク前の姿がカッコよかったです。
- ――第1話で印象に残ったシーンはどこでしたか?
- 石川 悪夢を見た後の一連のセリフですね。ツエルブが「またあの夢をみたの」と尋ねてきたやりとりの中で、ナインは「あいつらは弱かった。だから死んだ」「俺たちも弱かった。だから助けられなかった」「今の俺たちは、違う」と言います。ここは第1話の非常に大事なシーンだと思ったので、あえてさらりと言ってみました。これはナインが、自らの過去と決別して、これから行動を起こそうという一種の宣言だと思います。でも、それをいかにも宣言風に言ってしまうと、ちょっとかっこ悪いかなと。『残響のテロル』は絵と音と脚本の力がすごく強いので、この発言の重さ・大きさについては、むしろそういうほうにお任せして、僕自身はサラッと演じました。試行錯誤しながら、何度も演じさせていただいたこともあって印象に残っています。
- ――アフレコの雰囲気はいかがですか?
- 石川 アフレコは、スタジオの制限時間いっぱいまでめいっぱい時間をつかって収録しています。今回は渡辺監督が音響監督も兼ねられていて、合間にブースに入ってきて、キャラクターの心情や設定について丁寧に説明してくださいます。士気の高い現場ですね。あと第1話の香盤表を見て思ったんですが、外画を中心に活躍されている方が多くて、非常に豪華なメンバーなんです。そうういう方たちとマイク前に立てるの喜びも加わって、なるべく作品に貢献できたらいいな、と思ってアフレコに臨んでいます。
- ――ファンの方へメッセージをお願いします。
- 石川 『残響のテロル』は非常におもしろい作品で、それは関わっているスタッフ・キャストにおもしろい人が揃っています。僕のインタビューの前に掲載されているスタッフのインタビューや、これから掲載されるインタビューも併せて読んでいただけると、『残響のテロル』を一層楽しんでいただけるはずです。

- ――オーディションがあったそうですね。
- 斉藤 僕はオーディション現場に早めに入るタイプなんですが、その日は珍しく自分が決めた時間より遅めになってしまって、オーディション会場まで走っていったんです。結構暑い日で、息を切らしながら会場についたら、オーディションの進行が巻いていて「すぐ始められます」と。それでゼーハーいいながら、ブースに入って読んだ第一声が「あちーな、しかし」(笑)。僕のその時の嘘偽りない気持ちでした(笑)。
- ――それはすごい偶然でしたね(笑)。
- 斉藤 まあ、それはおもしろ話なんですけれど(笑)。真面目な話をすると、その時に渡辺(信一郎)監督からは、ツエルブというのは見た目のとおり素直で優しいようでいて、それだけではない部分があるので、ナチュラルな中に異質さを意識してほしいと言われました。
- ――ナチュラルな中に違和感、というのはなかなか難しいですね。
- 斉藤 そうなんです。ナチュラルであってはほしいんだけれど、ただの高校生がしゃべっているようにはしないでほしい、と。そのバランスは今もいつも意識しています。
- ――第1話、第2話と演じて、いかがでしたか。
- 斉藤 リサの学校に転校してきて、挨拶でいきなり「ジャンボ!」って言いますけど、相当ですよね(笑)。『残響のテロル』には変わったキャラクターばっかり出てきますが、ツエルブはその中でもかなりとらえどころがない方なんだなと。ツエルブの中では何か流れがあってそういう行動をとっているはずで、そう思って一貫性を持って演じようとはしているんですが、まわりの方から見ると、なかなかそうは見えないですよね。あと、ツエルブって、時々えげつない顔をするじゃないですか。あれは、本当にそういうえげつない部分があるのか、それとも純粋さ故の残酷さなのか……。それが本当はどっちかは本編をご覧になって確かめてほしいんですが、僕自身もツエルブが一体どんな人間なのか、そこを興味深く思いながら演じています。
- ――斉藤さん自身は、自分とツエルブに重なる部分はあると感じていますか?
- 斉藤 うーん、僕は何か行動起こす時にもうまくいかなかったことを考えて、自分の中に予防線を引くタイプなんですよ。だから、自分の性格とはあまり重ならないと思っていたんですが……PVを見た友人たちは「ホントに君のまんまだね」と言うんですよ(笑)。別に普段から「ジャンボ!」とか「おつカレーマルシェ」とか言っているわけではないのに!(笑)。何か表から見ただけじゃない部分があるように見えるのかな、とも思います。そういう意味では思ったまま行動しているツエルブくんの自由さには憧れるところはありますね。
- ――第1話でツエルブはリサのことをナインに委ねます。ツエルブはリサのことをどう思っているんでしょう。
- 斉藤 第2話までの段階だと「何かおもしろそう」と思っているんじゃないかなぁ。第1話で「くるりん、かわいい」って言っていたのとそう変わらない素直な感覚で、リサをなんかちょっとおもしろそうって思っているんでしょう。実は第3話以降で、リサと印象的な会話をするシーンが出てくるんですが、そこのツエルブのお芝居はニュアンスが難しくて何度も録り直しました。リサとのやりとりでは、そこも印象に残っています。重いテーマの作品ですが、僕としてはそこに生きているのは等身大の人間という部分を大切に演じていきたいと思っています。
- ――斉藤さんはアニメが好きだそうですね。
- 斉藤 そうですね……。あんまり公に言ってこなかったんですけれど、僕は渡辺監督の『カウボーイビバップ』『サムライチャンプルー』を見て育ったようなものなんですよ。特に高校生の時に見た『カウボーイビバップ』で、初めて“渋さ”というものを意識したんです。渡辺監督はその後の『サムライチャンプルー』『坂道のアポロン』などでも、周囲の環境や人々に翻弄されながらも譲れないものを持っている人の姿を描いていて、それが渡辺監督のテーマのひとつなのかもしれないな、と思っています。あと、渡辺監督の作品といえば菅野よう子さんの音楽!2話までご覧いただいた方はおわかりだと思いますが、今回も菅野さんの音楽は本当に素敵です。
- ――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。
- 斉藤 『みなさんの「これからこうなるんじゃないかな」という予想はたぶん裏切られると思います(笑)。それぐらい毎回予想外のことが起きるので。だからいっぱい予想して、物語に翻弄されることで、物語の深いところを感じてもらえればと思います。

- ――柴崎というキャラクターについて、渡辺信一郎監督からはどういう説明があったんでしょうか。
- 咲野 実は僕はテープオーディションしか受けていないんですよ。ほかの人はテープオーディションの後に、渡辺監督の前でもう1回オーディションがあったそうなんですけど。だから、第1話のアフレコの時が監督との初対面で、オーディションの時はこれという話は聞いてないんです。ただ、オーディション原稿がかなりボリュームがあったんです。中には「これは物語のクライマックスに出てくる大事なセリフなんじゃないか?」っていうようなセリフまで入っていて。だから、キャラクターをつかむという意味では、すごくわかりやすいオーディション原稿でした。それでOKになったのだから、キャラクターのとらえ方としては、そう違っていなかったのかなと思ってます。
- ――では、第1話のアフレコはいかがでしたか。
- 咲野 第1話のアフレコ前に渡辺監督に確認したのは、閑職においやられている柴崎は、あきらめて今の立場を受け入れているのか、それとも不満をもっているのか、ということです。それによってその後のお芝居がみな変わってくるので。そこについては、「過去のいきさつも含めて、柴崎は納得ずくであそこにいる」と説明があり、それでいろいろ決まっていったところはあります。あとは……オーディションでは、難しいセリフも多くて、ずいぶんと小難しいことをしゃべるな、と思っていたんです(笑)。どこでこんなに喋るんだと。ところが第1話は、ほとんどセリフがなかった(笑)。将棋指してるぐらいですからね。
- ――それは第2話以降の謎解きのシーンだったわけですね。
- 咲野 そうなんです。第2話の後半から脳ミソがフル回転をしていくんですよね。今さら名をあげるつもりはないでしょうけれど、正義感は強いでしょうから、そういう自分が奮い立つ瞬間を待っていたのかもしれません。
- ――謎解きの情報量の多いセリフというのはやはり難しいんでしょうか。
- 咲野 そこについては渡辺監督と意見が同じでしたね。「本人の主張とかを込めているセリフではないので、目の前にあるものを淡々と読むように」ということだったんですが、僕も同感で、情報量だけでおなかいっぱいになっちゃうところなんで、その上に余計なものはいらないよな、と。第3話以降、そういうセリフは増えていくんですが、自分の中ででてきた柴崎の言葉を口にするだけで、そういう意味では余分な工夫はなしで演じてます。
- ――柴崎の感情面の表現については、なにか意識していることはありますか。
- 咲野 これは渡辺監督から言われたことですが、激昂するシーンがあっても、それは状況に対してある意味冷静に当たりを見回して怒鳴っているんであって、我を忘れて怒るようなことはしないでほしいといわれました。感情的なシーンというのは、演者もやり過ぎてしまいがちなんですが、ちゃんと空気を読んだお芝居をしてほしいといわれました。
- ――石川界人さん、斉藤壮馬さんという若手の方と絡むシーンが多いですが、いかがですか。
- 咲野 この前の「ノイタミナ」でやっていた『ピンポン』の時も、若手の中に一人交じるみたいな状況だったんですよ。その時にも、思いましたが、若い人の反射神経っていうのは素晴らしいですよね。自分なんかは、事前に理論武装してから現場に向かわないと臨機応変にできないんですよね。彼らは、フットワークがいいんですよね。一度演じて、修正が入ると「ああっ」といって、さっと演じますからね。
- ――理論武装というのは、どういう準備をするんですか?
- 咲野 つまり台本を読んで自分が受け取った印象について、なぜそういう印象を持ったのか、感覚だけじゃなくて、頭の中で整理することですね。もし「なんでそう演じたの?」って聞かれたら「これこれこういう根拠が台本にあって、それでこう考えたからだよ」と言えるようにしておくということです。そういう説明が必要だっていう意識が、世代的なものなのか、あるんですよね。それは必要だと思うからやっているわけだけれど、逆にそのために自分の理論から抜け出せなくなる時もあるんですけれどね。僕らは、作家さんの書かれたものを脳で受け取ろうとするんだけれど、若者はそれを心で受け取ってるような気がしますね。
- ――視聴者の方にメッセージをお願いします。
- 咲野 『残響のテロル』って実際の生活にすごく“near”な作品だと思います。登場するキャラクターは、電車で隣り合わせにいてもおかしくないぐらリアルな存在感を持っているんだけれど、ギリギリアウトでそこから外れている人ばかりなんですよね。その中にあって柴崎は、昭和の価値観、昭和の正義感の代表だと思います。だから僕らの世代から見て、共感できる部分が多い。なので、僕と同じぐらいの世代の人は(笑)、是非柴崎のその昭和っぽさに注目してほしいですね。

- ――第4話から第5話にかけて、ついにリサが動き始めます。演じるにあたって渡辺信一郎監督からは、どんなキャラクターだと説明がありましたか?
- 種﨑 「この世界のどこにも居場所がない女の子だ」と言われました。ほかにももう少しお話はあったのですが、私は、この「居場所がない」ってところだけを心に残して演じました。リサという女の子の手がかりは、この一つだけで十分だったというか。
- ――ただその「居場所のない感」を出すにしても第1話、第2話とリサのセリフはすごく少ないですよね。
- 種﨑 そうなんです。その分、息芝居が多くて、しかも表情変化もいっぱいあって。細かいところまで描かれているその映像に引っ張ってもらいながら演じていた気がします。あと息芝居はすごくおなかを使うのを実感しました。演じているうちにおなかが鳴ることも多くて……。ノイズになっちゃったりして、ごめんなさいということもあったのですが、最近はご飯を食べる時間を工夫して、それでおなかがなることはほとんどなくなりました。
- ――完成した第1話をご覧になっていかかでしたか。
- 種﨑 音楽で鳥肌が立ちました。第1話はアフレコの時に既に絵が出来あがっていたんです。だから映像としては同じなのですが、音楽や効果音がついたら「これは映画!?」って思うようなすごい作品になっていて。そこから自分の声が聞こえるのが不思議でした。
- ――オーディションの様子はどうたったんでしょうか。
- 種﨑 オーディションは今回事前に原稿をいただいていたのですが、当日行ったら「今日はこれになりました」と事前にいただいていたものと違う原稿をいただきまして(笑)。でもセリフが変わってもリサという子は変わらないので。自分が作ってきたリサのことを考えながら無心で演じました。色々考える時間がなかったのが逆に良かったのかもしれません。
- ――オーディション演じ終わって、手応えはありましたか?
- 種﨑 ほんとに無心だったので、あまり覚えていないんです(笑)。でも、リサに決まったという知らせを聞いた時、「ヤッホーッ」(笑)ってすごくうれしい舞い上がる気持ちと同時に、腑に落ちるというか「うん」と小さく頷くような感じもあって、しっくりくる感触はありました。
- ――第4話からまたリサが動き始めます。リサの変化をどんなふうに受け止めましたか。
- 種﨑 最初はずっと下を向いているキャラクターなんだなと思いました。そうしないといけない状況にいる子なんだと。でもそんな状態の中で、リサにとっての希望が、ツエルブという姿でプールへと飛び込んできたのが第1話だったと、私は思います。この時、リサの中に自分が変わるかもという予感もあったのかな。あのツエルブがプールに飛び込むシーンは、第1話のラストでリサ自身がツエルブのところにダイブするシーンと対になっているそうで、私自身一番印象に残っているシーンです。それで、第3話までは様子をうかがいながらいる感じで、声を出すときも、喉に何か詰まっているような感じだったんです。それが第4話でツエルブにつられて笑ったところで吹っ切れて。第5話からは素直にその場にいるようになります。第5話のアフレコでは、柴崎役の咲野さんに「リサってこんな子だっけ(笑)」と言われました(笑)
- ――第4話で吹っ切れたんですね。
- 種﨑 そうだと思います。第1話の「死にたくない」とか第3話の家を出るとか、人間の本能で動いている感じだったのですが、吹っ切れてからは自分の意思で動いている感じがします。それまでのリサとは全然違うかなと思います。
- ――種﨑さんから見てナインとツエルブはどんなキャラクターですか。
- 種﨑 リサから見ると、自分の世界をかえてくれる人だと思います。ただ第4話でリサは、そういうふうに感じる自分をずるいと思うと言ってますけれど……。私から見ると、ナインの態度は一貫していて信用?出来るのですが、ツエルブは無邪気だったり怖かったり、どっちなんだとドキドキします(笑)でもリサからすると、手を差し伸べてくれたのはツエルブなので、そういう安心感はあるのかな、と。
- ――今後の展開というのは……。
- 種﨑 全然分からないんです。これから3人はどうなっていってしまうのか。また新キャラクターも出てきたりするので、先を考えようとしてもしきれないです。実際、ここまでも台本を見るたびに驚きの連続でしたし。でも、最高に繊細で最高におもしろい作品になると思いますので、視聴者のみなさんもラストシーンまで一緒に見届けていただけたらうれしいです。

- ――ハイヴを初めて見た時、どう思いましたか?
- 潘 オーディションの前にキャラクターデザインを見ていました。日常的なデザインが多いこの作品の中で、ハイヴはどこか浮いていて、いい意味で異様なところに魅力を感じていました。セリフにしても自分ではなかなか言えない、この役を通じてじゃないと言えないものが多かったので、オーディションの段階から面白そう、演じてみたいと思っていました。
- ――役が決まったあと、どのように演技されましたか?
- 潘 最初は彼女の見た目から受ける印象を演技に反映しました。15歳だけど妖艶で、職業も核の研究者という大人のキャラクター。ただ、渡辺監督からは可愛らしく、それでいて怖いことを平気で言う小悪魔的なキャラクターでお願いしたいというディレクションが入り、自分が作った演技から監督の求める演技に近づけるため、一度葛藤がありました。その「可愛らしさ」も監督の中と自分の中にあるものが違い悩みましたね。ハイヴの持つ、一見すると怖いけどその中にある可愛さを自分の演技や声で出すのが難しかったです。
- ――アフレコ現場はどんなかんじでしょうか?
- 潘 「残響のテロル」は監督が音響監督も兼ねる作品です。アフレコ現場では渡辺監督の求めていることが直接わかるので緊張します。他にも、先輩が多かったり、女性も少ない現場なので、そういったことでも緊張しますね。
- ――毎話、アフレコに時間がかかる現場ですよね。
- 潘 収録時間が長ければいいというわけではないですが、時間をめいいっぱい使う、妥協のない現場です。ここでOKが出されたら自分でも後悔が残る、という時、「テロル」はいつまでも付き合ってくれます。なので、かかる時間が長いのもうなずけます。
- ――作品をみた感想をお聞かせ下さい。
- 潘 作品のタイトルから抱いていた印象をはるかに超える、「想定外」の作品でした。ナインとツエルブが起こす「テロ」も想定外だし、そこに関わっていく人々の動きも想定外。特に女性キャラクターがナイン・ツエルブの予想を越える動きをしていて、リサ・ハイヴもストーリーの流れの中ではある意味テロリストですね(笑)
- ――ハイヴもテロリストですか?
- 潘 ナイン・ツエルブにとってハイヴは施設を脱出した際、死んだと思ってた人物です。そんな彼女が出てくるのがまず想定外。そして驚異的な存在として自分たちの計画を邪魔してくるのは、彼らにとって「テロ」なのだと思います。
- ――他にどんなご感想を抱かれましたか?
- 潘 実際の場所や日常の音、役者さんの演技・呼吸、そして流れてくる音楽が合わさって凄くリアルな映像だと感じています。キャラクターのセリフ1つ1つにしても実際の人間の口元と一致していて、一人ひとりの瞬き、目の伏せ方、歩き方をとってもリアリティが詰まっています。ナインとツエルブが爆弾を作っている場面なんかでは、物の質感やキャラクターの手つき、その場所の音や声の響きから現実以上にそこにあるものを感じとることができます。作品の中の世界が、自分の住んでる世界と別とは思えないぐらいです。
- ――7話までで印象に残っているシーンを教えてください。
- 潘 2話のオープニング終了後、爆発された都庁のニュースが流れるんです。その後、CMが終わった後に今度は街の風景が流れるんですが、事件から何日もたっていないのに何事もなかったかのように日常が流れている。空は晴れていて、ビルも道路も何事もなく描かれている。2話の前半と後半で間逆な世界が描かれていて、そのことが逆にリアルでした。あれだけの事件があって人々が驚いているのに、何事もなかったかのように日常は過ぎていく。日常と非日常のギャップが画面に出ていますが、そこにある差が逆にリアルに感じました。どこかで事件が起きて、ニュースで報道されたりするけど、普通に日常は続いているという残酷さが第2話では描かれていたなと思います。特に、リサが見上げた先にある崩れた都庁が印象的でした。
- ――視聴者にメッセージをお願い致します
- 潘 「残響のテロル」の出来事は決して他人事ではなく、いつどこでこういうことが起きてもおかしくないと思いながら見ています。皆さんもアニメ作品だけど、こういうことが現実に起こるかもしれない、と思いながら見ていただけるとありがたいです。そして、ぜひ振り返って何度でも見てください。このシーンにはこんな意味があったんだ、この時キャラクターはこんなことを思っていたんだ、日常だけどこんなことを示唆していたんだ、と見終わったあとでも色んな事に気づき、感じることができる作品です。
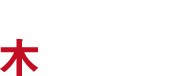
- ――プロデューサー目線で見たこの作品の魅力を教えてください。
- 木村 「残響のテロル」は原案者である渡辺信一郎監督の作家性が軸となっている企画です。ノイタミナとしては「坂道のアポロン」という企画と共にご一緒することが決まりました。初めて企画のプロットを見た時は興奮しました。局としての立場でいうとヒヤヒヤする側面もありましたが、だからこそいろんなチャレンジに満ちていて、消費されずに残っていく企画になるような期待感がありました。中でもやはり「核」という題材を真正面から描いていることがポイントだったと思います。今の時代でエンタメに昇華することが難しい題材に、これはあえて立ち向かっていく企画なのだと思いました。
ただ、私が「残響のテロル」で最も魅力的だと思っているところはそこではなく、そんな時代の風を意識して作っているにも関わらず、普遍的なテーマが真ん中に置いているところです。その詳細はまだ言えないのですが、最後までこの作品を見ていただければきっとお分かり頂けると思います。
- ――作品を作る上で楽しかったこと、逆に大変だったことは?
- 木村 シナリオ制作は楽しかったです。たとえば爆破のギミックを考える際、いろいろな専門家の方々に取材させて頂いたのですが、ほんとに自分が知らないだけで危険はすぐ近くにあるんだなあ、と勉強になりました。その取材を元に攻防を考えていくのですが、監督やライターさんとシナリオを作っているとまるで悪い計画を立てているみたいになってきて…傍からみるとちょっと危険な人たちになっていたかもしれません。
大変だったのは、あんまりアニメっぽくない作品なので、メインビジュアルを考えるところで苦労しました。ロボットがいればロボットを背負わせられるし、剣を持っていたら剣を構えさせられる。でもこの作品は…、というところで苦労しました。
- ――今後の見どころを教えてください。
- 木村 スピンクス達や刑事の柴崎、アメリカから派遣されたハイヴにはそれぞれ立場を超えた目的があります。それは彼らのルーツに関係していたり、スピンクス達が盗み出したプルトニウムに関連しています。
テロとは本来何らかの要求や思想とセットだと思います。しかし、彼らはまだプルトニウムというとても危険なものを所有しながら爆破を繰り返すだけで、何の要求も出していません。
第8話以降は、それぞれのキャラクターのルーツが交錯しながら、スピンクスがプルトニウムを強奪した理由が、明らかになっていきます。第7話まではそれらをほとんど明かさずにゆっくりと伏線を張ってきたので、第8話以降のスピード感のある展開が見どころになってくると思いますね。
- ――視聴者の方へメッセージをお願いします。
- 木村 この企画は最終話で真価が問われると思います。
ぜひ、最後までご覧いただき、それぞれのキャラクターの物語としての結末を見届けていただければと思います。

- ――第11話まで演じ終えての感想を教えてください。
- 石川 あっという間でしたね。時間にしたら全11話という話数は決して長くないです。でも、すごく濃い時間を過ごしたなという感覚があります。楽しい時間はあっという間に過ぎていってしまうんだなと思っています。
- 斉藤 僕は、まだ終わってしまったという感覚がないです。毎週のアフレコがそれぐらい自分にとって重要な時間になっていたので、自分の中で終わってしまったことが信じられないというのが正直なところですね。
- ――第11話のアフレコ台本をもらった時の第一印象を教えてください。
- 石川 その時は、ふわっと「ああ、これが最終回なんだ」という気持ちになりました。ラストも柴崎とリサの会話ですっと静かに終わっていきますし。
- 斉藤 僕はやっぱり「あぁ、死んでしまった」と思いました。その前に、危なそうなところでもなんとか助かっていたので、余計にそう思いましたね。
- 石川 ああ、死に様についてはいろいろ思いますね。僕は、ナインはどんな顔で死んでいったのだろうかと、そこは気になっているんです。
- 斉藤 そうだね。ナインの死を客観的に見せる描写はなかったものね。
- 石川 ナインの主観の視点で、意識を失っていく様子はあるんですよね。
- 斉藤 それでナインが倒れた後、鳥たちが飛び立っていくという。
- 石川 ああ、思い出してみても、やっぱりナインの最期の顔をちゃんと見てみたかったなぁ。
- 斉藤 ……もしかしたら死んでいないかもしれない?(笑)
- 石川 いやいや、あんな立派なお墓まで立てられていて、そんなんだったらみんなから怒られますよ(笑)。
- 斉藤 (笑)
- 石川 でも、真面目な話をすると、ラストカットは二人が死んでしまったということ以上に、「本当にこんな出来事があったんだろうか」「二人は本当にいたんだろうか」って思わせるような、そういう雰囲気がありましたよね。それもあって最初に台本読んだときは、ふわっとした気持ちになったんです。
- 斉藤 目の前の光景の中に鳥の羽がふわっと浮かび上がっていく映像は、主観的なビジョンとして何度も出てきているものですよね。渡辺(信一郎)監督はそのビジョンをどうしてラストにおいたのか。そこはすごく気になるところです。
- 石川 そうそう。ラストがそういう表現になるってわかっていると、そこへ向けて演技を作っていけばいいとわかるので、その点ではやりやすかったです。
- 斉藤 第11話で僕が印象的だったのはもう一つあって、1年後を表現するのにリサのナレーションを使っていたことです。この作品は、登場人物のモノローグや、どんな心境なのかを説明するセリフがとても少ないんですよね。それだけに特別な感じがあって。
- 石川 ナインを演じていても、モノローグが少ないっていうのは感じましたね。ナインのようなタイプのキャラクターって、モノローグで自分の感情を説明したりすることも多いんです。でも、それがない。キャラクターがその時何を思っているかは、解釈する演技者と、受け止める視聴者の方にかなり委ねられているんです。その分、やりがいもあったし、より深くキャラクターに入り込めることができたので、モノローグが少ないのはうれしかったです。
- ――誰もいない二人が育った施設跡で遊ぶシーンも印象的でした。
- 斉藤 世界の終わりを感じさせる廃墟で遊ぶというイメージはよかったですね。
- 石川 アフレコの時はまだ絵が正式なものでなかったけれど、それでも荒廃している感じはすごく伝わってきたし、すばらしいなと思いましたね、直前の、原爆が爆発した後の街の風景のところは完璧に絵が入っていたので、それを見てBパートに入っていけたので、やりやすかったです。ただ施設跡で遊ぶシーンは、いいシーンなんですけれど、音楽シーンなんでセリフないんですよね(笑)。
- 斉藤 (笑)あそこに限らず、第11話は僕らセリフが少なかったよね。ナインなんて特に。ほんとに喋ってないよね。
- 石川 そうなんだよね。事前に渡辺監督に「最終回は(セリフが)あるよ」っていわれて、「いや、セリフがあるとかないとかそういうことでは」と思いましたね(笑)。終わったあとで、改めて監督から、セリフ少なくてごめん、といわれました(笑)。
- ――第11話に至るまでのドラマを振り返りたいと思います。ツエルブは第8話以降、ナインと別行動になりますよね。
- 斉藤 ナインと袂を分かってでもリサを助けにいく、という決断はツエルブにとっては大きかったと思います。でもツエルブの本質が純粋なキャラクターであることは変わっていません。ただ、その純粋さがどう発露していくかが変わっているので、ツエルブの見え方というのが変わっていくんです。それでリサに対しては――距離の取り方はちょっとおかしかったりはするんだけど――ただただ大切にしたいと思う部分が見えてきた。そういう中での第8話だったと考えています。ただツエルブがそうなっていけばいくほど、ラストまでちゃんと生き延びられるかは心配にはなりました。だから最終回、台本をもらっても、しばらくはちょっと読みたくないな……という気分で。
- 石川 でも、それはツエルブがいい役だったということだよね。
- 斉藤 それはそう。いい役やらせてもらったなって本当に思いました。
- ――そして、続く第9話は観覧車のシーンが印象に残っている人も多いと思います。
- 斉藤 そうですよね。
- 石川 僕は「ツエルブ」4文字しかセリフがなかった回ね(笑)。
- 斉藤 その4文字にはちゃんと魂こもっていたよ(笑)。
- 石川 原爆を学校から持ち出すシーンも、息を入れないし(笑)。
- 斉藤 (笑)。リサとはそれまでにも何度か対話をしてきたんだけれど、ツエルブはリサに自分のことを語らないんです。そのツエルブが爆弾を解除しながら、こんなことになるなら君に声をかけなければよかったんだと言う。そこにすごく真に迫るものがあるなと。
- ――さらにハイヴから電話がかかってきます。
- 斉藤 あそこでハイヴから電話がかかってきたことで、ハイヴのいうことを受け入れるか入れないかというサスペンスにシフトするんです。あそこでツエルブはリサと一緒に死ぬという選択肢もあったけれど、そうではなく一緒に生きることを選んだ。ツエルブ自身の残り時間は少ないけれど、時間がないからこそ世界を見ていたいという気持ちですね。
- ――ツエルブと別行動になったナインは、どう考えていたんでしょうか。
- 石川 ナインは、どんな状況になってもツエルブが死ぬとは思っていなかったと思います。あれは気持ちが離れているわけではないので。僕は今回、合間をみていろいろ渡辺監督に質問したのですが、そこでナインはなぜリサを突き放すのかについても話題にしました。そこでは、ナインもリサを守りたいと思っているからだ、という話になったんです。確かに自ら行動を起こして能動的に守るのはツエルブです。でも、ナインもリサを守りたいと思っていた。だから遠ざけようとしていたんだよと。
- ――行動は違っても目的は同じということですね。
- 石川 ツエルブが出て行く時に、ナインはそれを止めようとします。でもツエルブが行ってしまった以上はリサを守ると信じていたでしょう。そしてそれは自分の思っていることでもある。ツエルブを信じているからこそ、第10話で淡々と原爆の準備をしているのだろう。そう思って演じました。
- ――そして第10話では、ハイヴに追われるナインをツエルブが救う展開があります。
- 石川 あそこは……ツエルブが助けてくれなくてもナイン一人でなんとかなったかもしれない(笑)
- 斉藤 えー(笑)。それならもうナイン一人でやればいいんじゃないかな(笑)。そうしたらツエルブはリサといっしょに学園で、「最近物騒だよね」とかいいながら過ごすから(笑)。
- 石川 そうなるよね(笑)。
- ――第11話では、そこについてナインがツエルブにお礼を言っています。ちょっと珍しいシーンかなと思ったのですが。
- 石川 いや、そこはあまり特別には感じませんでした。ナインとツエルブとはずっと会話をしてきたし、ナインが感情をまず見せるのはツエルブなので、あのセリフには違和感はなかったですね。
- 斉藤 それにしても第10話のラストの「日本の皆さん、さようなら」ってすごいセリフだよね。「最後の爆弾は原子爆弾です」だし、ね。やっちゃったな、って思ったね。
- 石川 思ったね。日本の歴史を振り返っても、原子爆弾ってすごくインパクトを持った強い言葉なんですよね。このインパクトの強さは、ギリギリかなと思った。
- 斉藤 第10話の時点では、どう使うのかは知らされていないからよけいにインパクトあったよね。
- 石川 そういえば、実は僕たちだけは、第1話・第2話のころ爆弾をどういうふうに使うのかだけは知らされていたんですよね。
- 斉藤 そうなんですよ。高高度爆発とか電磁パルスについても説明受けました。
- ――「日本の皆さん~」のセリフを言うときに、気に掛けたことはありましたか?
- 石川 言い方を考えるということはしてません。セリフは物語の流れの中で演じるものなので。ただ、これは自分が自首した後の展開を想定し、事前に準備されていた映像なので、そこまでの流れとは違ったように聞こえてほしいなと考えました。ト書きにあった「不敵な笑みで」とあった通りに聞こえてくれればいいなと思いました。
- ――シリーズを通して印象的だった会話があれば教えてください。
- 石川 ほんとにずっと一緒にいたツエルブには申し訳ないけど……(笑)、第10話とのハイヴとのやりとりですね。
- 斉藤 その前振りいらないから(笑)
- 石川 (笑)。ハイヴが死ぬところは、潘さんと何度もやらせてもらったんですが、やるたびに潘さんから出てくるものが違って、僕もなんとかそこに追いつこうと思って必死になって演じました。最終的に満足いくお芝居できたテイクがOKになって、すごく気持ちが入ったシーンでした。セリフを「言う」ではなく、「吐くことができた」と感じられたシーンでした。
- ――ツエルブのほうはどうでしょう
- 斉藤 僕も、ずっと一緒に演じていることが多かったナインさんには申し訳ないんですが(笑)、リサとのやりとりですね。
- 石川 やっぱり、女の子とのシーンをあげるんだ。
- 斉藤 ナインもな(笑)
- 石川 そのツッコミを待っていた(笑)。
- 斉藤 リサとの対話は要所要所にあるんです。公園での会話があって、バイクのシーンがあって、観覧車のシーンがある。特に観覧車のシーンは、極力抑えた芝居をした繊細なシーンだったので、印象に残ってます。……あと、リサといえば第5話と第8話のご飯回の印象的でしたけどね(笑)。フレンチトーストをあんなに焦がす人は見たことがない(笑)。
- 石川 ナインは食べる前からマズイって言っていたし(笑)。
- 斉藤 (笑)。それで、第10話ではリサに「ツエルブの馬鹿」って言われるんですけど、ツエルブは何かのきっかけをリサからもらうことが多かったです。もしナインとツエルブがリサに会っていなかったら、ただ黙々と作戦をこなしただけで、今みたいな変化は起きていなかったと思う。
- 石川 うん。まったく変わらなかっただろうね。
- 斉藤 でもその分、情にほだされることもなく、淡々と目的を完遂していたかもしれない。でも、そうはならないのが物語のおもしろいところだよね。
- 石川 うん。変化ということでいうと、僕は第9話の、原爆のありかを言っちゃって、うなだれているツエルブ好きなんだよね。
- 斉藤 ガラス越しにこうなってる(実際に自分でポーズをとっている)ところだよね。
- 石川 本当にガックリきてる感じが伝わってきたんだよね(笑)。
- ――最後に全編を見終えたファンの方にメッセージをお願いします。
- 石川 僕らもまだ、終わったんだというふわっとした感想しか持てずにいます。そういう感覚を見終わったばかりのみなさんと共有できていればいいなと思っています。そしてラストを見てからまた全編を見直すと、新しい発見がある作品です。映像のクオリティも高いので、パッケージなどで何度も見返していただければうれしいです。
- 斉藤 見終わったばかりだと「『残響のテロル』とは、こういう作品だった」と言い切ることが難しいと感じている方もいると思います。いろいろ詰まっている作品なので、僕自身、そういう気持ちです。だからこそ少し時間をおくと、違った見方・感じ方ができるようになって、ある時、腑に落ちる瞬間が来るのだと思います。これからも折に触れてこの作品を思い出していただけるとうれしいです。

- ――最終話の制作を終えた時のご感想をお聞かせください。
- 渡辺 ずっとテンパった状態で制作してたんで、完成してもなかなか終わった気がしなくて。1週間ぐらいは「あのカットのリテイク直さないと!」という夢にうなされて飛び起きる、って感じでしたね。一ヶ月ぐらいたって、やっと終わった実感が出て来たかな。
- ――制作や放送が終わったら、すぐに気持ちが切り替わるわけではないのですね。
- 渡辺 この作品は企画を考えてから、つまりキャラクターとか世界観が生まれてから放送するまでずいぶん時間がかかってるんです。だから、放送としてはたった3ヶ月だけど、自分的にはもう5、6年前からこの作品と付き合ってきてるので、そんなにパッと切り替わらない。放送が終わっても、それはずっと自分の中で生きていくものだしね。
- ――今回は、いつになくメッセージ性が強いというか、政治的な要素も強かったと思うんですが、何故こういうスタイルになったのでしょうか?
- 渡辺 自然に出てきたものですね。というか、過去の作品にもそういう要素はあるんです。それがよりダイレクトな出方をしてるという。
- ――何故ダイレクトになったんでしょう?
- 渡辺 自分に限らず作り手っていうのは、その時代の空気を吸って、その変化を敏感に感じ取って生きているわけだから、時代の流れがそうさせたんでしょう。今現在、それこそ先の戦争というものが本当に忘れられてしまって、次の戦争を志向する人が権力を持ち、戦争というものの尻尾が見えてきている、そんな時代に生きているのに政治的にならないほうがどうかしてるんじゃないかな。もちろん、時代がそこまで切迫してなければダイレクトには出ないと思うんだけど。
- ――ナインとツエルブの最後は、企画の当初から決まっていたのですか?
- 渡辺 ストーリーの最初と最後は、最初の企画段階から決まってました。主人公が、限定された時間のなかで何をやるべきだと考え、何を残していくのか、そういう話をやりたかった。でも彼らは特別な存在という事ではなくて、限られた時間を生きるという事においてはあらゆる人間が同じわけだから、これは誰にでも当てはまるテーマだと思ってます。
- ――彼らが特別な存在だからテロを起こしている、というわけでもないのですか?
- 渡辺 自分たちの存在を否定するものがいて、その相手がものすごく大きなものであった時に、戦うことを諦めるのか、それとも怯まずに戦うのか。このテーマはナインとツエルブに限ったものではありません。彼らは戦うことを選びましたが、例えば私達も国がやっていることがおかしいと思ったとき、デモをやっても無駄だと諦めることもできれば、何か行動を起こすこともできる。そういった意味では二人は特別な存在ではなく、この作品も現実と地続きのテーマを持っています。
- ――だから舞台も東京という現実にしたのですか?
- 渡辺 今まで作ってきた作品でも、現実と無関係なファンタジーを作ってきたわけではありません。未来や江戸時代の形を取りながらも、現代の今を生きている人間を描いてきたつもりです。でももっと現実と地続き、ストレートにつながっているものを作りたいと思いました。
- ――アフレコのことをお聞かせください。
- 渡辺 普段のアフレコって、音響監督を別に立てる形が多いんだけど、今回は役者たちと直接、やりとりをしてみようかなと。彼らが感じてる事、疑問点、なども直接ぶつけてもらって、話し合いながら役を作っていくというやり方がしたいなと思って。今回は作品の内容もセンシティブだし、ちょっとした微妙なニュアンスが重要になってくるんで、自分が直接やり取りしたほうがいいかなと。実際やってみたら、すごくやりやすいし、良かったですね。役者陣の考えもダイレクトに伝わってくるし、こういう所を気にするんだ、という発見もあったり。
- ――確かにアフレコは石川さん・斉藤さん中心に質問が度々かわされ、気合を感じた現場でした。
- 渡辺 石川・斉藤・種崎・藩というメインの四人はみんな若くて、すごくやる気に満ちてるしパワーがありました。単に彼らに指示通り演じてもらった、という感じじゃなくて、一緒にそれぞれのキャラクターを作っていけたんじゃないかな。彼らからキャラクターにフィードバックされていったものも多いと思います。あとは、若手をサポートしつつこの作品を支えたのは咲野(俊介)さんですね。セリフまわしとか言い方を、けっこう勝手に変えてくるんですよ(笑)。でも聞いてみて、たしかに柴崎だったらこう言うかな、という所が多かった。やっぱり、自分なりの柴崎を考えてきてるんだなと。あと、咲野さんはこの作品の演技の指針になったとこがあるんじゃないかな。例えば「リアルに」とか「ナチュラルに」とか言ったところで、具体的にどの位でやればいいのか、その度合いを決めていくような役者がどの作品にもいて、今回は彼がその役をやってくれたと思いますね。セリフもやたら多いし(笑)。
- ――今後もBD&DVDが発売されていきますが、改めて「残響のテロル」を見る際に注目して欲しい箇所を教えて下さい。
- 渡辺 映像的には、微妙な色合いや明るさにもこだわってるし、ほんの僅かな光の具合がわかる、良い画面で改めて見て欲しいですね。あと、特に注目してほしいのは音です。効果音とかセリフを含めた音の響きから音楽まで、音響全般に関してこだわりすぎるぐらいこだわっているので、Blu-ray&DVDの良い音質でぜひ聞いて欲しいですね。
- ――最後に、作品を終えたメッセージをお願いします。
- 渡辺 昔から、余韻が残る作品が好きなんです。例えば昔の映画とかテレビドラマって、見終わってハイ終わり、じゃなくて、終わった後も、いろんなディテールを思い出したり、時には何年も後になってふと思い出したりするような事があったんです。今回、そういう作品が作れたんじゃないかなと思ってます。タイトルのように「残響」が残っていくような作品を。